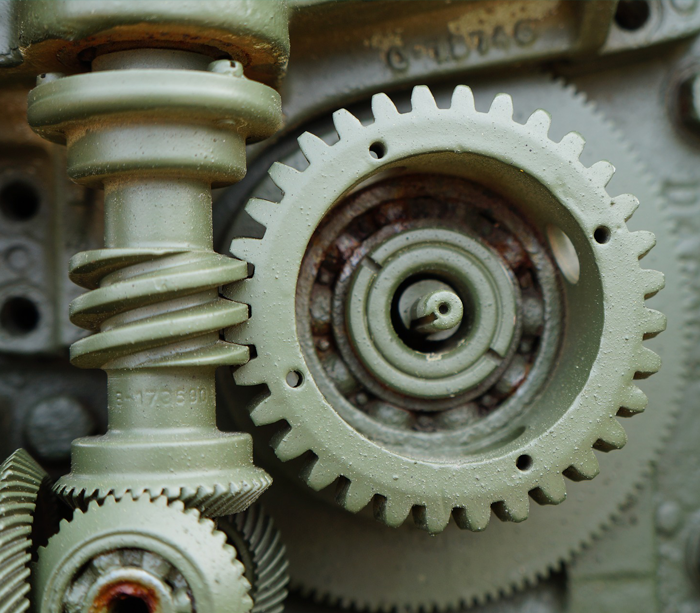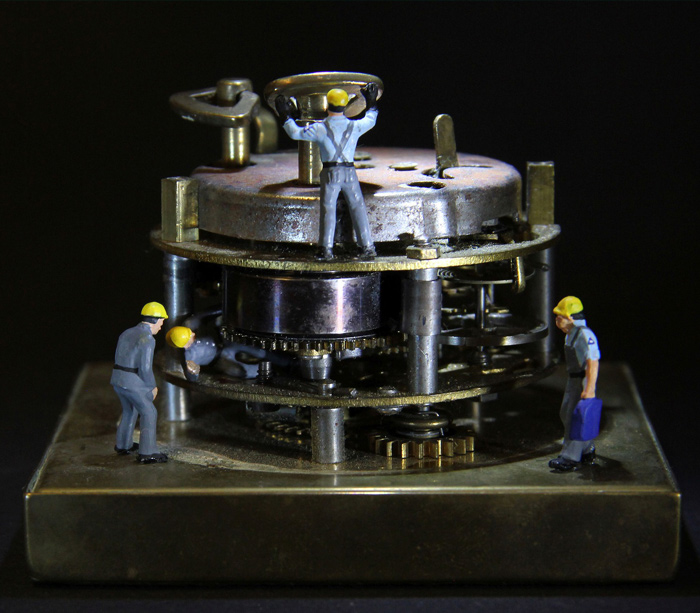新型コロナウイルスの影響で在宅勤務をしている方も多くいるのではないでしょうか。在宅のメリットはたくさんありますがデメリットもあり、その中に運動不足があります。今まで通勤や会社内での移動で運動をしていた方は、運動不足を感じていませんか。
その悩みIoTで解決しましょう。
そんな人のために正しいポーズを教えてくれるウェアラブル「NADI X Smart Yoga Pants」が発売しています。
使い方は簡単です。
・レギンスのようなウェアを履く
・専用のアプリとウェアをBluetoothで接続
・アプリに表示されているポーズと同じポーズをする
・正しいポーズをとれていないとバイブレーションでお知らせ
とっても簡単ですね。これなら手軽に使用でき、正しいポーズでヨガをすることができますね。
「WELT」はベルト式なので、普段通りにベルトを付けることで、ウエストのサイズを測ることができます。
ウエストを測るだけではなく、長時間座りっぱなしで動いていない時間も計測してくれアラームでお知らせをしてくれます。その他にも食べ過ぎてウエストを緩める動作も記録してくれるので、食べ過ぎを防止したい人にはうれしい機能ですね。
弊社では、新規開発の依頼を承っております。「こんな製品出来ないかな」「こんな技術があるけど、コラボレーションできないかな」など何でもお気軽にお問い合わせください。

その悩みIoTで解決しましょう。
ヨガの正しいポーズを教えてくれるウェアラブル
自宅で動画や本を見ながらヨガを始めてもこのポーズであっているのか分からないときありませんか。私は、なんか違うと思うときが多々あります。そんな人のために正しいポーズを教えてくれるウェアラブル「NADI X Smart Yoga Pants」が発売しています。
使い方は簡単です。
・レギンスのようなウェアを履く
・専用のアプリとウェアをBluetoothで接続
・アプリに表示されているポーズと同じポーズをする
・正しいポーズをとれていないとバイブレーションでお知らせ
とっても簡単ですね。これなら手軽に使用でき、正しいポーズでヨガをすることができますね。
ベルトをするだけでウエスト計測
ウエストのサイズを毎日測っていますか。測らないですよね。でも、自分が今どれくらいウエストのサイズがあるのか知りたいですよね。いざウエストを図ろうとしてもメジャーを探したり正確なサイズを測ることが出来なかったりしませんか。「WELT」はベルト式なので、普段通りにベルトを付けることで、ウエストのサイズを測ることができます。
ウエストを測るだけではなく、長時間座りっぱなしで動いていない時間も計測してくれアラームでお知らせをしてくれます。その他にも食べ過ぎてウエストを緩める動作も記録してくれるので、食べ過ぎを防止したい人にはうれしい機能ですね。
まとめ
家にいながら運動をサポートしてくるのはうれしいですね。自分ではなかなか気づけない座りっぱなしや姿勢など教えてくれるので、運動しようという気持ちになりますね。弊社では、新規開発の依頼を承っております。「こんな製品出来ないかな」「こんな技術があるけど、コラボレーションできないかな」など何でもお気軽にお問い合わせください。