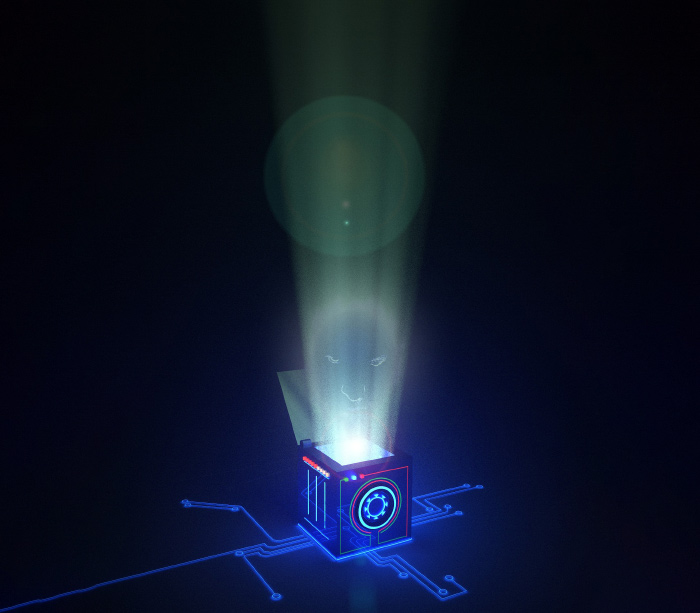最近弊社 IoTゲートウェイ一体型ハードウェア(FLEX H/W)を利用した屋外用センサリング機器をプランニングしている中で先方から、こんな質問が有りました。
未発表なのでここではLTE回線で直接サーバーにデータ送信する物を【スマート○○】、現地インターネット環境に接続する通信網を【Wi-Fi○○】とします。
質問内容は
【通信料がスマート○○ Wi-Fi○○ にも必要でしょうか。】
説明不足で申し訳ないなと思い、通信回線とWi-Fi※無線LAN通信についてこんな風に回答した所、理解頂けた様子で少し反省しております。
通信回線とwi-fi通信の関係は下記のようになります。
設備費用 電波の元(インターネット環境)〜通信設備までの間wi-fiの構築が必要
設備費用 直接つなぐので不要※携帯電話の電波が届く所しか設置できない
あまり気にしたことが無かったのでインターネットや携帯回線(5G・4GLTE)と Wi-Fi(無線LAN)通信の違いを少し説明させていただきます。
①Wi-FiとはWi-Fi親機、Wi-Fi子機をつなぐ近距離対応の通信技術で通常無線LANというの方が理解し易い<かもしれません、Wi-Fi規格に対応していれば様々な機器間で接続できる機器間の通信で外部のインターネット接続は無くてもデータのやり取りが可能です。
イメージとしては機器同士をLANケーブルでつなぐ所を無線でつなぐ形です。
使用電波としては主に2種類あり
「2.4GHz帯」は障害物に強く対応機種が多い半面混雑する為、通信が遅い傾向に有ります。
「5GHz帯」は電波干渉が少なく、安定した高速通信傾向に有りますが、あまり遠くには繋がりません。
②インターネットや携帯回線(5G・4GLTE)については、ここではデータをサーバーに送る為の無線通信部分を説明するとIoTと称する物のインターネットの世界では取得したデータをサーバーに送信する事で様々な事を行うので、現地の機器とサーバーをつなぐ通信が必要となります。
これについては、スマートフォンの様に携帯回線を使用する事も出来ますし、家庭や会社等の光回線等をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
一般的にはIoTとは、「Internet of Things = モノのインターネット化」とわかりにくいかもしれませんが、皆さんの身の回りにあるIoT製品について身近なIoTはよく目にすると思います。
物+つながる+インターネット環境=【スマートフォン】
弊社は、名古屋でIoTの開発・販売を行っています。
「こんなところにIoTを導入できないかな?」「この悩みIoTで解決できないかな?」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
未発表なのでここではLTE回線で直接サーバーにデータ送信する物を【スマート○○】、現地インターネット環境に接続する通信網を【Wi-Fi○○】とします。
質問内容は
【通信料がスマート○○ Wi-Fi○○ にも必要でしょうか。】
説明不足で申し訳ないなと思い、通信回線とWi-Fi※無線LAN通信についてこんな風に回答した所、理解頂けた様子で少し反省しております。
通信回線とwi-fi通信の関係は下記のようになります。
wi-fi(無線LAN)通信の場合
通信費用 お客様の通信を利用するので不要※設置箇所にインターネット環境が有る設備費用 電波の元(インターネット環境)〜通信設備までの間wi-fiの構築が必要
4G LTEの場合
通信費用 直接つなぐので必要※通信容量で月額が変わる(携帯電話のイメージ)設備費用 直接つなぐので不要※携帯電話の電波が届く所しか設置できない
あまり気にしたことが無かったのでインターネットや携帯回線(5G・4GLTE)と Wi-Fi(無線LAN)通信の違いを少し説明させていただきます。
①Wi-FiとはWi-Fi親機、Wi-Fi子機をつなぐ近距離対応の通信技術で通常無線LANというの方が理解し易い<かもしれません、Wi-Fi規格に対応していれば様々な機器間で接続できる機器間の通信で外部のインターネット接続は無くてもデータのやり取りが可能です。
イメージとしては機器同士をLANケーブルでつなぐ所を無線でつなぐ形です。
使用電波としては主に2種類あり
「2.4GHz帯」は障害物に強く対応機種が多い半面混雑する為、通信が遅い傾向に有ります。
「5GHz帯」は電波干渉が少なく、安定した高速通信傾向に有りますが、あまり遠くには繋がりません。
②インターネットや携帯回線(5G・4GLTE)については、ここではデータをサーバーに送る為の無線通信部分を説明するとIoTと称する物のインターネットの世界では取得したデータをサーバーに送信する事で様々な事を行うので、現地の機器とサーバーをつなぐ通信が必要となります。
これについては、スマートフォンの様に携帯回線を使用する事も出来ますし、家庭や会社等の光回線等をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
一般的にはIoTとは、「Internet of Things = モノのインターネット化」とわかりにくいかもしれませんが、皆さんの身の回りにあるIoT製品について身近なIoTはよく目にすると思います。
物+つながる+インターネット環境=【スマートフォン】
弊社は、名古屋でIoTの開発・販売を行っています。
「こんなところにIoTを導入できないかな?」「この悩みIoTで解決できないかな?」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。