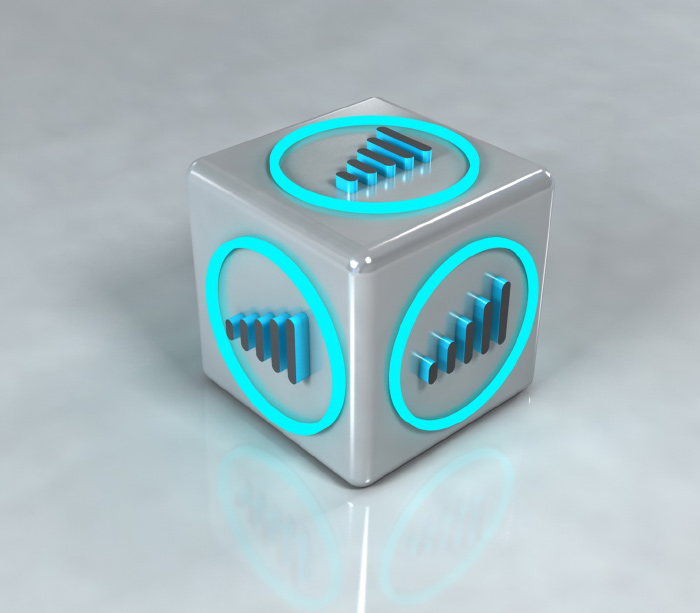この度、株式会社MTLは経済産業省「2021年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業」において、補助金の代理申請を行うIT導入支援事業者に採択されました。
※2021年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業とは、中小企業・小規模事業者等が抱える課題の解決に向けてITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する際、かかる費用の一部を補助し、業務効率化・売上アップをサポートする制度です。
令和2年度第3次補正からはこれまでの通常枠(A・B類型)に加え、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)も追加されました。
私たちはIoTと自動化の提案企業として、今後ともお客様の生産性向上に貢献するIT導入をご支援いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

※2021年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業とは、中小企業・小規模事業者等が抱える課題の解決に向けてITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する際、かかる費用の一部を補助し、業務効率化・売上アップをサポートする制度です。
令和2年度第3次補正からはこれまでの通常枠(A・B類型)に加え、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)も追加されました。
IT導入支援事業者とは?
補助事業を申請者とともに実施する、補助事業を実施するうえでの共同事業者(=パートナー)を「IT導入支援事業」と呼びます。交付申請の仕方
補助金の交付申請は、弊社をはじめとするIT導入支援事業者による代理申請のみ受付となっています。私たちはIoTと自動化の提案企業として、今後ともお客様の生産性向上に貢献するIT導入をご支援いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。