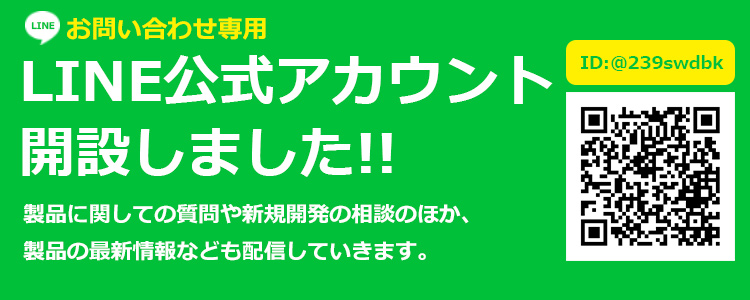IoT技術を使った家電などが身近に増えていますよね。でも、IoTとは何?と思っている人も多いと思います。
なので、今回は、IoTの仕組みや活用事例をご紹介いたします。
今まで通信機能を搭載していなかったモノに通信機能を搭載してインターネットに接続させています。
IoTを活用することで遠隔地から対象物を計測・制御したり、モノ同士で通信を行うことが可能になります。なので、様々な分野での活用が期待されています。
IoTでできることは下記の4つです。
・離れた場所からモノを動かす
・離れた場所からモノの状態が分かる
・モノや人の動きを検知できる
・モノとモノを繋げることができる
IoTを活用することで離れた場所のデータを送受信することができるためリアルタイムでモノだけではなく人の状態も把握するために利用されています。
例えば、スマートスピーカーに話しかけるとテレビや電気などの家電を操作することができます。
工場内の機器をインターネットに接続しデータを収集します。収集したデータを分析することで生産性や設備の稼働状況などを可視化することができます。
それにより、生産性をあげるために施策や改善をすることができます。
ハウス栽培なら日射量や土壌の状態に関するデータを収集して分析することで水やりなどの作業を自動化したり、温度や湿度の調整をすることができます。
農業分野は、スマート農業の実現に向けてIoTだけではなくICTなどの最先端技術の導入も進んでいます。
ウェラブルデバイスを使うことで、脈拍や心拍、血圧などを計測でき取得したデータを医師にリアルタイムで共有が可能です。
IoTは身近にある家電だけではなく工場内でも省人化や効率化に向けて活用しています。IoTで生活が楽になれば自分の時間が増えるのでどんどん活用していきたいですね。
弊社は、名古屋でIoTの開発・販売を行っています。
「こんなところにIoTを導入できないかな?」「この悩みIoTで解決できないかな?」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

なので、今回は、IoTの仕組みや活用事例をご紹介いたします。
そもそもIoTとは何?
IoTとは「Internet of Things」の略で「モノのインターネット」と訳されています。今まで通信機能を搭載していなかったモノに通信機能を搭載してインターネットに接続させています。
IoTを活用することで遠隔地から対象物を計測・制御したり、モノ同士で通信を行うことが可能になります。なので、様々な分野での活用が期待されています。
IoTの仕組み
IoTの対象となるモノには、センサーやカメラ、無線機能が搭載されています。モノの状態や動きを感知してデータを取得します。取得したデータをインターネットを介して人やモノに伝送することがIoTの基本的な仕組みです。IoTでできること
基本的な仕組みが分かったところでIoTでできることをご紹介します。IoTでできることは下記の4つです。
・離れた場所からモノを動かす
・離れた場所からモノの状態が分かる
・モノや人の動きを検知できる
・モノとモノを繋げることができる
離れた場所からモノを動かす
例えば、出先から家のエアコンの電源を入れ部屋を快適にしたり、消し忘れた部屋の照明を消したりできます。そのほかにドアの鍵を閉めたり、ペットの餌を決まった時間に自動であげたりできます。離れた場所からモノの状態が分かる
例えば、出先から部屋の照明の状態や室温を確認できます。また、ペットの首輪から運動量や食事量に関するデータを取得することでペットの健康状態を把握することもできます。IoTを活用することで離れた場所のデータを送受信することができるためリアルタイムでモノだけではなく人の状態も把握するために利用されています。
モノや人の動きを検知できる
例えば、電車やバスの混雑状態を把握したり、人の動きに合わせて照明をつけたり消したりすることができます。モノとモノを繋げることができる
モノとモノをつなぐことをMtoMといいます。例えば、スマートスピーカーに話しかけるとテレビや電気などの家電を操作することができます。
IoTの活用事例
製造業での活用
製造業では、生産ラインの省人化や効率化のためにIoTが活用されています。工場内の機器をインターネットに接続しデータを収集します。収集したデータを分析することで生産性や設備の稼働状況などを可視化することができます。
それにより、生産性をあげるために施策や改善をすることができます。
農業分野での活用
製造業と同じで生産ラインの省人化や効率化のためにIoTが活用されています。ハウス栽培なら日射量や土壌の状態に関するデータを収集して分析することで水やりなどの作業を自動化したり、温度や湿度の調整をすることができます。
農業分野は、スマート農業の実現に向けてIoTだけではなくICTなどの最先端技術の導入も進んでいます。
医療分野での活用
医療分野では、着用型のウェアラブルデバイスの活用が進んでいます。ウェラブルデバイスを使うことで、脈拍や心拍、血圧などを計測でき取得したデータを医師にリアルタイムで共有が可能です。
まとめ
今回は、IoTでできるとこをご紹介しました。IoTは身近にある家電だけではなく工場内でも省人化や効率化に向けて活用しています。IoTで生活が楽になれば自分の時間が増えるのでどんどん活用していきたいですね。
弊社は、名古屋でIoTの開発・販売を行っています。
「こんなところにIoTを導入できないかな?」「この悩みIoTで解決できないかな?」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。