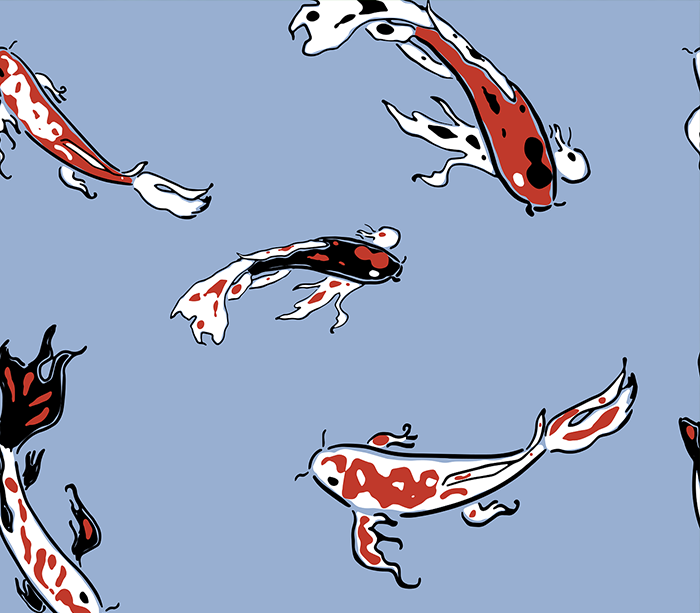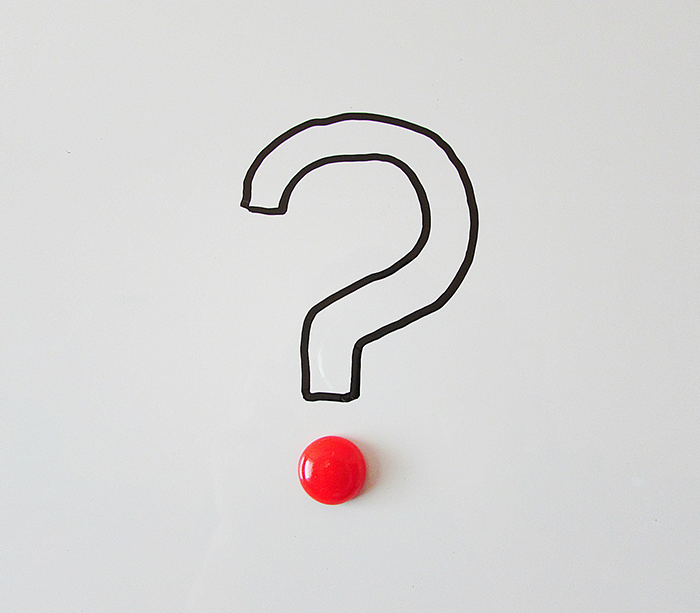企業やお店では、IoTを活用しているところが多くありますが、私たちの身近なところでもIoTは活用されています。
今回は、身近にあるIoTをご紹介していきます。

IoTは「Internet of Things」の略で、モノのインターネットと呼ばれています。
従来、インターネットに接続できるのは主にパソコンと携帯電話、スマートフォンなどに限定されていましたが、IoTは通信端末に限らずセンサー、タグなどを通して、エアコンや冷蔵庫といった家電や自動車、ドローンなどの産業用の大型設備などがインターネットにつながります。
IoTはまず、IoT化されたデバイスが搭載されている、温度・湿度、照度などのセンサーからデータを取得します。取得したデータは、インターネットを通してクラウド上に蓄積していきます。蓄積されたデータはAIなどによって解析され、デバイスが最適制御されることでユーザ一人ひとりにあったサービスを提供してくれます。

身近な活用事例を見ていきましょう。
電子マネーやスマートフォンで購入すると、購入者の情報を読み取りその人にあった商品をおすすめすることができます。
あらゆるモノがインターネットに繋がれば私たちの生活が今までより快適になっていくでしょう。
弊社でも新規開発の依頼を承っております。「こんな製品出来ないかな」「こんな技術があるけど、コラボレーションできないかな」など何でもお気軽にお問い合わせください。

今回は、身近にあるIoTをご紹介していきます。
IoTって何ができるの?

IoTについて説明できますか?
従来、インターネットに接続できるのは主にパソコンと携帯電話、スマートフォンなどに限定されていましたが、IoTは通信端末に限らずセンサー、タグなどを通して、エアコンや冷蔵庫といった家電や自動車、ドローンなどの産業用の大型設備などがインターネットにつながります。
IoTはまず、IoT化されたデバイスが搭載されている、温度・湿度、照度などのセンサーからデータを取得します。取得したデータは、インターネットを通してクラウド上に蓄積していきます。蓄積されたデータはAIなどによって解析され、デバイスが最適制御されることでユーザ一人ひとりにあったサービスを提供してくれます。
身近な活用事例

家をIoT化!?スマートハウスとは
自動販売機の電子マネー
街などで見かける自動販売機に電子マネーやスマートフォンが使えるのは知っていると思いますが、IoTが活用されていることを知っていましたか。電子マネーやスマートフォンで購入すると、購入者の情報を読み取りその人にあった商品をおすすめすることができます。
人や動物などの動きを把握して、録画
不在時に不審な動きがあったら録画を開始してスマホに通知したり、警告音を鳴らしてくれたり、留守中に子供やペットを遠くから見守ることができます。最適なタイミングで水やり
プランターなどをIoT化すると植物の育成状態、土壌状態、水分量、光量などから植物ごとに最適なタイミングで適量の水を与えたり、光を与えたりすることができます。まとめ
身近な活用事例をご紹介しましたが、知っているIoTや知らないIoT活用がありましたか。知らないだけで、私たちの身近にはIoTが多く活用されていますね。あらゆるモノがインターネットに繋がれば私たちの生活が今までより快適になっていくでしょう。
弊社でも新規開発の依頼を承っております。「こんな製品出来ないかな」「こんな技術があるけど、コラボレーションできないかな」など何でもお気軽にお問い合わせください。