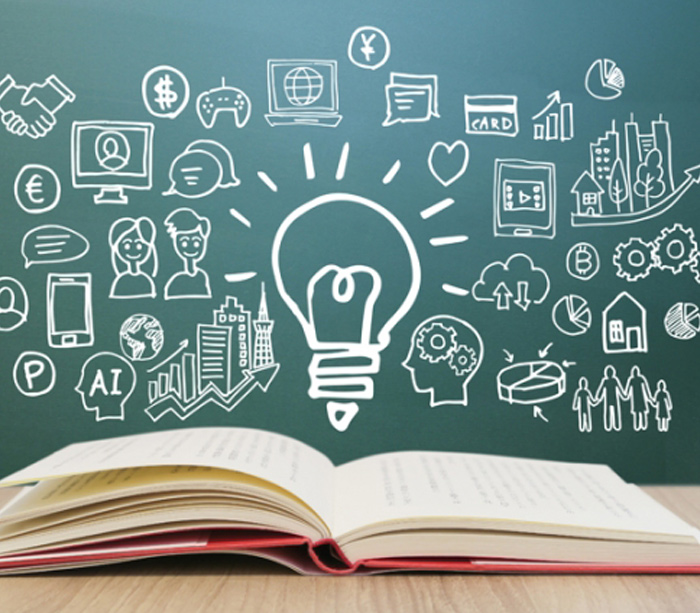今まで通信機能のなかった「モノ」をインターネットとつなげるIoT。最近では家電にも使われるようになり、身近に感じられるようになってきました。そのIoTを製造業に導入することで、多くの問題を解決することが期待されています。この記事では、IoT化によって得られる効果について解説します。
また、PCやタブレットからいつでもデータを確認できるので、資料作成や日報などの事務作業の負担が軽減します。IoTによる作業の効率化は、無駄な人件費やエネルギーコストを減らすことにもつながります。
多くの課題を抱える製造業がこれからも発展していくためには、IoTの導入は不可欠といえます。とはいえ、導入には機器やネットワークシステムが必要で、コストがかかるのも事実です。自社が必要とするところに無駄なく導入するには、豊富なノウハウをもつ専門企業に依頼するのがおすすめです。
弊社では、新規開発を承っています。「こんなアイディアがある」「こんな製品出来ないかな」「コラボレーションできないかな」などありましたらお気軽にお問い合わせください。ご相談もお待ちしております。
なぜIoTの導入が急がれるのか
現在の製造業は、人手不足による生産性の低下が著しくなっています。また、熟練の技術者が少なくなり、優れた技能や経験を引き継いでいくことができないという問題を抱えています。どちらも製造業の衰退を招きかねない大きな問題で、早急な対策が必要です。それらの問題の解決策として、IoTが期待されているのです。IoTが製造業の抱える悩みを解決する
では、製造業の現場にIOTを導入すると、どう変わるのでしょうか?ここからは、IoT導入で得られるメリットについて具体的に解説します。現場の状況を「見える化」する
設備や機器をインターネットとつなぐことで、現場の状況を明確に把握できるようになります。例えば、ラインごとの稼働状況や生産数などをガンチャートで表示するといったことが可能です。生産性の悪い作業、ボトルネック工程なども明確になるので、作業の改善に役立てることができます。作業の効率化とコスト削減
IoT化することで、今まで人がやっていた作業を減らして効率化できます。例えば、機器にセンサーを設置することで、不良品を自動で検出できます。機器の異常もすぐに検知することができ、トラブルを未然に防ぐことができるようになります。また、PCやタブレットからいつでもデータを確認できるので、資料作成や日報などの事務作業の負担が軽減します。IoTによる作業の効率化は、無駄な人件費やエネルギーコストを減らすことにもつながります。
蓄積したデータを活かせる
IoT化により得られたデータは蓄積され、売り上げの向上やロス削減に役立てることができます。例えば、受注数や在庫のデータから、最適な生産計画を自動で作成することも可能です。熟練者の技術やノウハウを数値化して残すこともでき、人材育成に利用できます。IoTの導入でさらなる発展を
IoTは、現場の状況を「見える化」することにより、業務の改善や効率化、コストカットなどを実現します。また、蓄積したデータを活かし、自社に最適な生産計画を立てたり、人材育成に役立てたりできます。多くの課題を抱える製造業がこれからも発展していくためには、IoTの導入は不可欠といえます。とはいえ、導入には機器やネットワークシステムが必要で、コストがかかるのも事実です。自社が必要とするところに無駄なく導入するには、豊富なノウハウをもつ専門企業に依頼するのがおすすめです。
弊社では、新規開発を承っています。「こんなアイディアがある」「こんな製品出来ないかな」「コラボレーションできないかな」などありましたらお気軽にお問い合わせください。ご相談もお待ちしております。